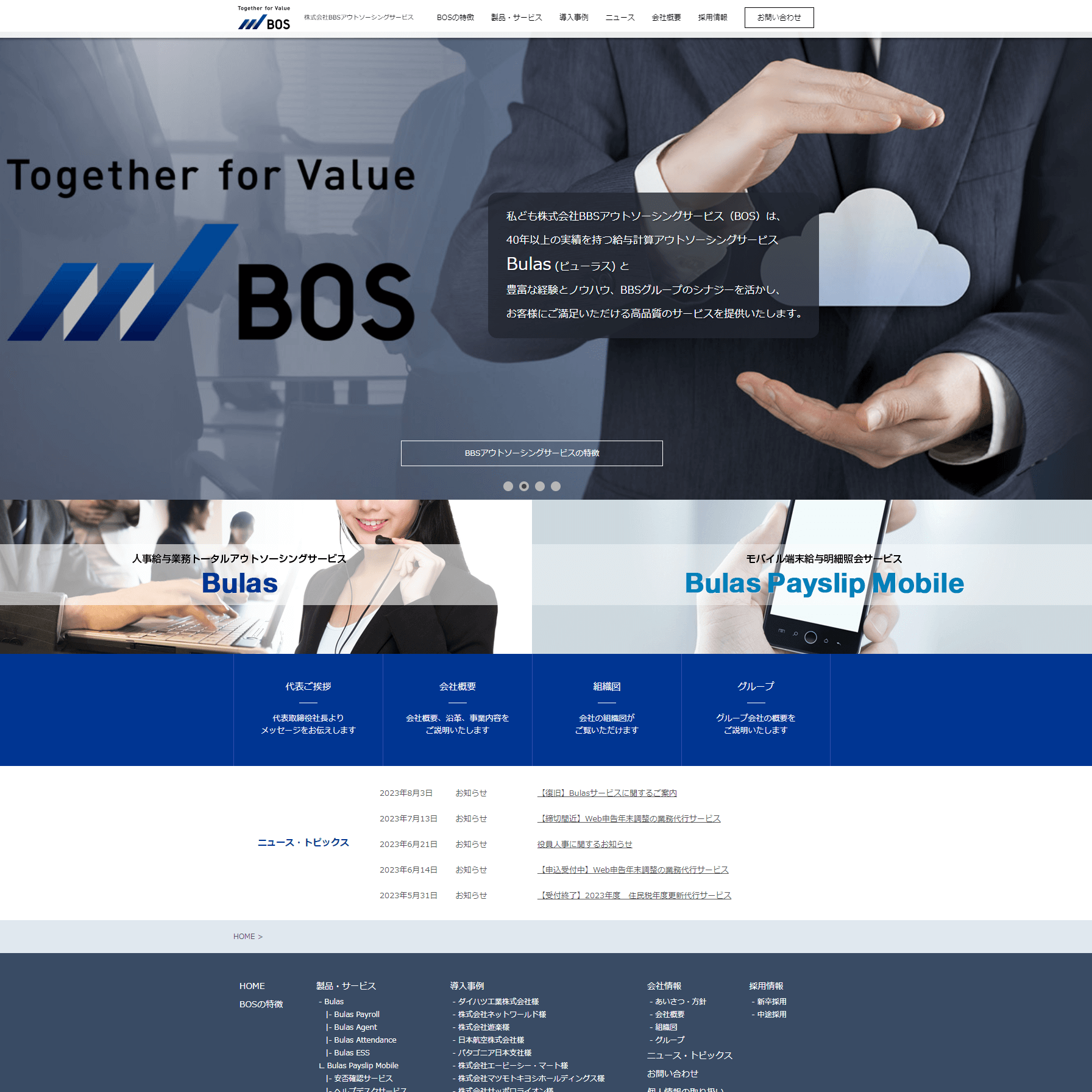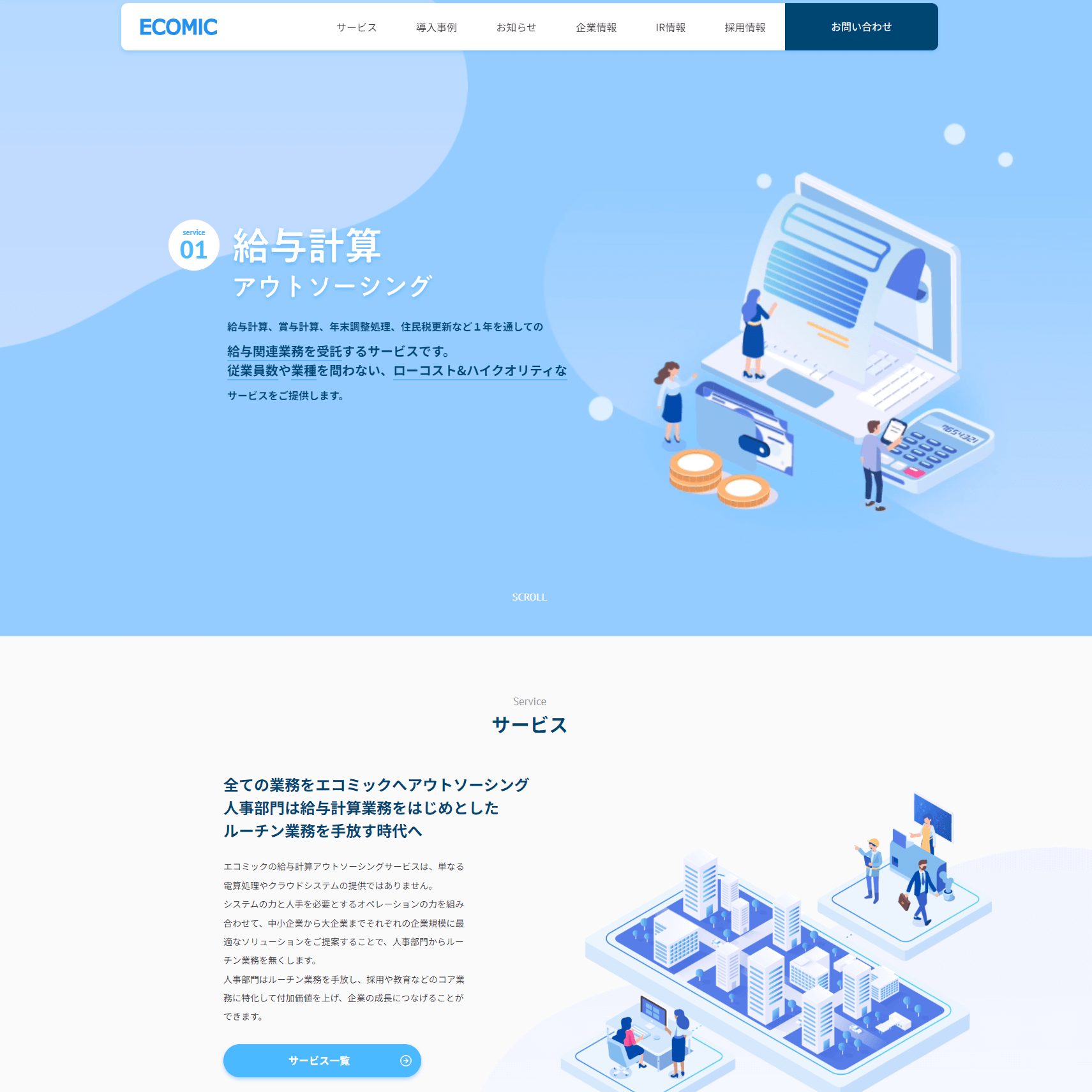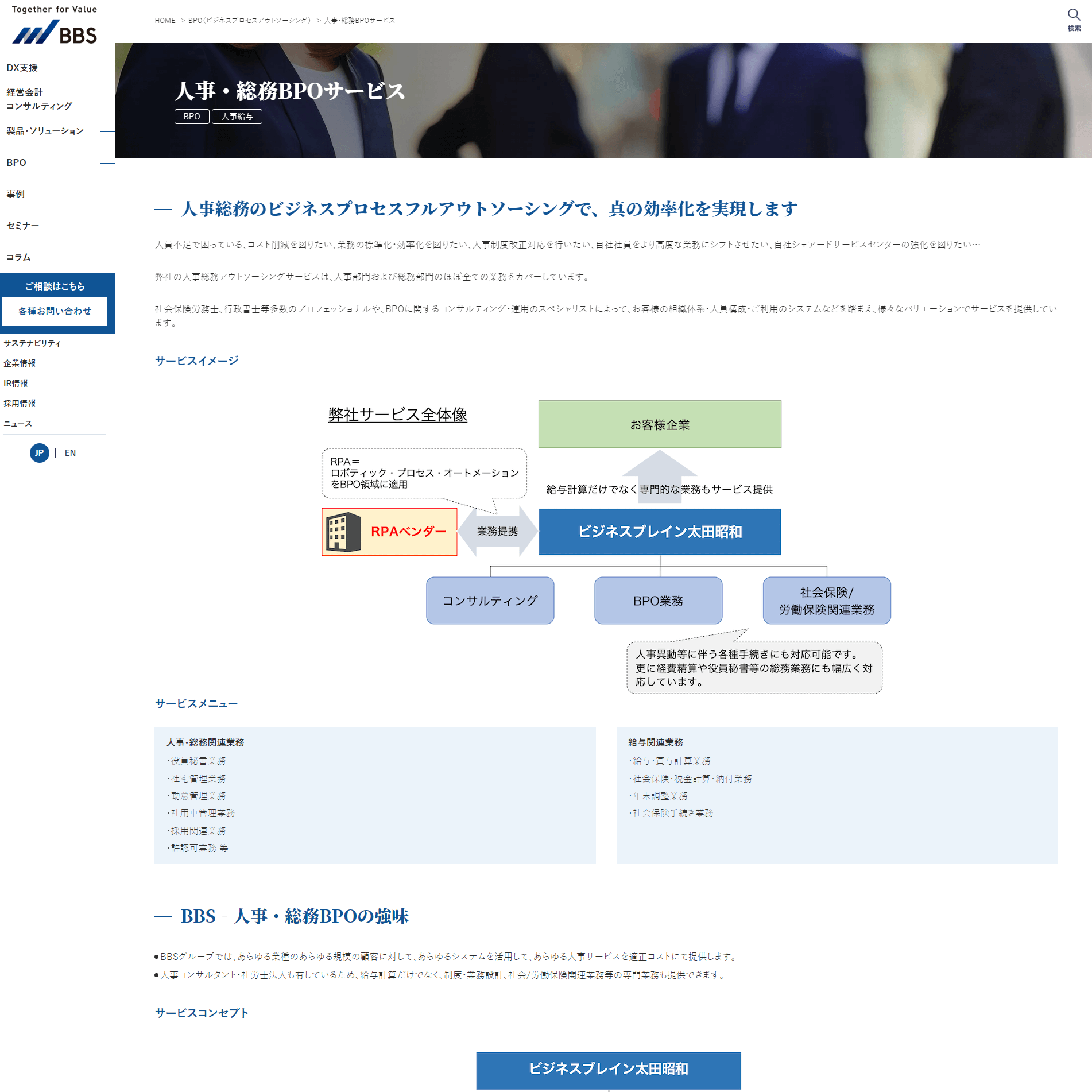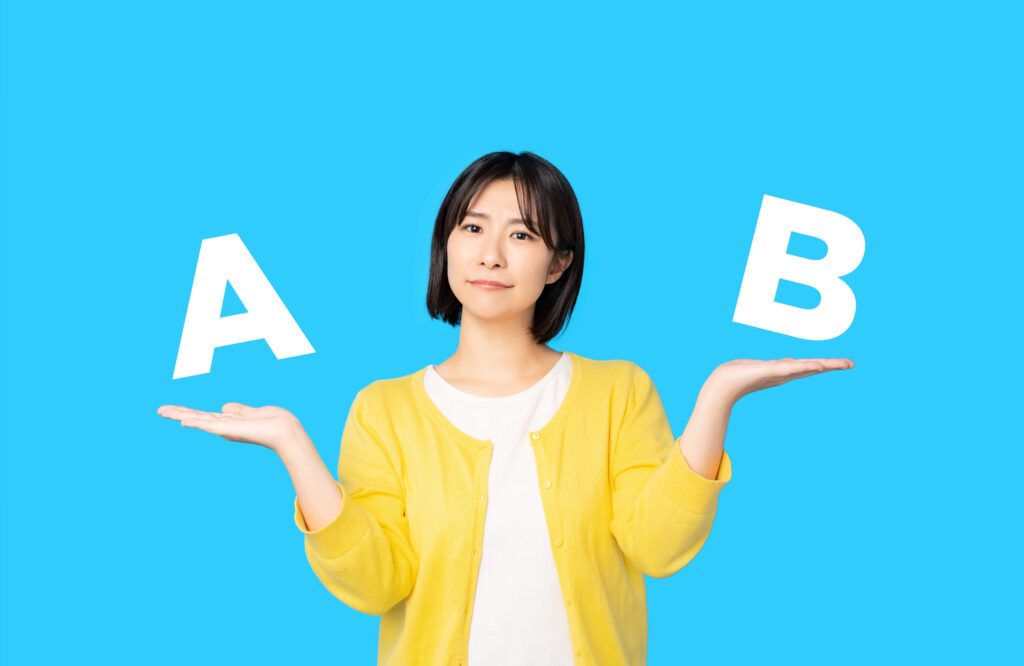雇用保険は、働く人々が安心して仕事に取り組めるように、失業した際に生活を支えるための保険制度です。労働者の生活を守る重要な役割を果たす雇用保険ですが、雇用側は対象者や保険料の計算方法を理解しておくことが大切です。
今回は、雇用保険の基本的な仕組みや対象者、そして保険料の計算方法とその注意点について、わかりやすく解説していきます。
CONTENTS
雇用保険とは?その対象者
雇用保険は、働く人が失業した場合や、育児・介護休業を取得する場合などに、生活費の一部を補助するための制度です。この制度により、労働者が職を失っても安心して生活できる環境が整えられています。
失業手当や育児休業給付など、さまざまな給付が含まれており、働く人の生活を支えるために重要な役割を果たしています。
まず、雇用保険の対象となる労働者について説明しましょう。雇用保険の対象となるのは、基本的に一定の条件を満たすすべての労働者です。具体的には、以下のような条件があります。
「週20時間以上働いていること」「31日以上雇用される見込みがあること」「パートやアルバイトも対象(一定の条件を満たす場合)」の条件に当てはまる場合は、雇用保険の対象内です。
このように、パートやアルバイトであっても、週20時間以上働いており、31日以上の雇用が見込まれる場合は、雇用保険に加入する義務があります。ただし、学生や日雇い労働者、短期契約の労働者など、一部の例外もあります。
また、65歳以上の高齢者や役員など、特定の職種や年齢層については、雇用保険に加入する義務がない場合がありますが、これについても条件によっては対象となるケースもあります。そのため、個々の雇用形態や状況に応じて、加入の要否を確認することが重要です。
雇用保険料の対象となる賃金と対象とならない賃金
雇用保険料の計算にあたっては、どの賃金が対象となるのかを正しく理解することが重要です。ここでは、雇用保険料の対象となる賃金と対象外の賃金について解説します。
対象となる賃金
雇用保険料の対象となる賃金は、毎月の給与や賞与額などが挙げられます。また、算定中に支払いが確定した場合も、雇用保険料の対象として参入しなければいけません。
そのほか、以下の賃金も対象となります。
1つ目は、通勤手当・定期券・回数券です。いわゆる通勤にかかる現物支給分は対象として適用され、通勤手当は非課税分を含みます。
2つ目は、超過勤務手当・深夜手当・宿直手当・日直手当です。「残業手当」というとわかりやすいかもしれません。
3つ目は、家族・子ども・扶養など、家族に関する手当です。配偶者や子どもがいる場合に適用されます。
4つ目は、技能手当・教育手当・特殊作業手当です。業務に活用できる技能や技術、資格を有している場合や子どもが学校に通う際の経済的負担を軽減するために適用される手当になります。
5つ目は、住宅手当・地域手当です。物価の高い地域に勤務する場合、雇用保険料の対象となります。
6つ目は、皆勤手当・精勤手当です。勤怠に関する手当のことで、勤務を奨励し、出勤を促進するために支給されます。
対象とならない賃金
一方で、雇用保険料の対象とならない賃金もあります。たとえば、役員報酬・結婚祝金・災害見舞金・勤続褒賞金・年功慰労金・退職金・休業補償費・傷病手当金などです。出張した際に支払われる旅費や宿泊費も、対象となりません。
また、30日前の解雇予告なしに従業員を解雇した場合の「解雇予告手当」も、雇用保険料が支払われないので注意してください。事前に知っておくことで、安心して雇用保険料を受け取れるでしょう。
ひとつ注意しておきたいのが「通勤手当」です。所得税の計算では対象外ですが、雇用保険料の計算では対象となります。超過勤務手当や深夜手当などで総賃金額が変わった場合も、雇用保険料が変動するので気をつけましょう。
雇用保険の計算方法
雇用保険料は、雇用される人と雇用者の双方が負担する形で成り立っています。保険料は、毎月の給与やボーナスをもとに計算され、給与明細から天引きされます。では、実際の計算方法を見ていきましょう。
まず、雇用保険料は、賃金総額に保険料率を掛けて計算されます。保険料率は年度ごとに見直されるため、毎年異なる可能性があります。一般的には、以下のような流れで計算されます。
賃金総額の確認
賃金総額には、基本給だけでなく、残業代や手当、通勤手当なども含まれます。基本的に「支給されたすべての給与」が計算の対象です。
保険料率の適用
雇用保険の保険料率は、事業の種類によって異なります。たとえば、一般事業、農林水産・清酒製造業、建設業で保険料率が異なります。
一般の事業は15.5/1,000です。(15.5/1,000です(2023年4月1日〜2024年3月31日))農林水産業・清酒製造業は17.5/1,000、建設の事業は18.5/1,000となっています。
保険料の計算
賃金総額にそれぞれの保険料率を掛け合わせて、労働者負担分と事業主負担分を計算します。労働者負担分は給与から控除され、事業主負担分は会社が負担する形で納付されます。
例として、月額賃金が30万円で保険料率が6/1,000の場合、労働者が負担する雇用保険料は以下のようになります。
30万円×6÷1,000=1,800
この場合、毎月の給与から1,800円が控除されます。なお、ボーナスについても同様に、支給額に応じて雇用保険料が計算されます。
計算する際の注意点
雇用保険料を計算する際には、いくつかの注意点があります。
まず、計算のもととなる賃金総額にはさまざまな手当や残業代が含まれるため、その範囲をしっかり把握しておく必要があります。たとえば、通勤手当や住宅手当、特別手当なども賃金総額に含まれるため、見落としがちな項目についても正確に計上することが重要です。
また、雇用保険料率は毎年度変わる可能性があるため、最新の情報を確認することも忘れてはいけません。保険料率が変わると、毎月の保険料額が変動するため、年度ごとに最新の料率をチェックし、それにもとづいて計算を行う必要があります。
さらに、事業の種類によって保険料率が異なるため、自分が働いている業種の料率を確認することが大切です。同じ雇用条件でも、業種によって保険料額が異なる場合があるため、所属する事業の正確な保険料率を確認しておきましょう。
他にも、雇用保険に加入するための条件を満たしているかどうかを定期的に確認することが重要です。とくに、パートタイムやアルバイトなど、労働時間や契約期間が変動しやすい労働者の場合、条件を満たしているかどうかの確認を怠らないようにしましょう。
また、65歳以上の従業員についても雇用保険の加入が必要です。勤務時間が変わったり、契約内容が変わる場合、雇用保険の加入条件も変わる可能性があるため、注意が必要です。
最後に、雇用保険に関連する法改正や制度の変更が行われることもあります。これにより、加入条件や保険料率、給付内容が変わることがあるため、定期的に法改正の情報をチェックして、最新の制度にもとづいた対応を心がけることが大切です。
とくに企業や事業主は、労働者に適切な手続きを行う責任があるため、常に最新情報にもとづいた対応を行うことが求められます。
まとめ
雇用保険は、働く人々にとって安心して働ける環境を提供するための重要な制度です。その対象者は広範囲にわたるため、パートやアルバイトであっても条件を満たせば加入する必要があります。
また、雇用保険料の計算方法は、賃金総額に保険料率を掛けるシンプルなものですが、業種や保険料率によって金額が変わるため、正確な計算が求められます。
さらに、計算時の注意点として、賃金総額の範囲や保険料率の変動、業種ごとの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。常に最新の情報をチェックし、正確な手続きと計算を行うことで、雇用保険制度を最大限に活用し、安心して働く環境を整えていきましょう。
-
 引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/
引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/