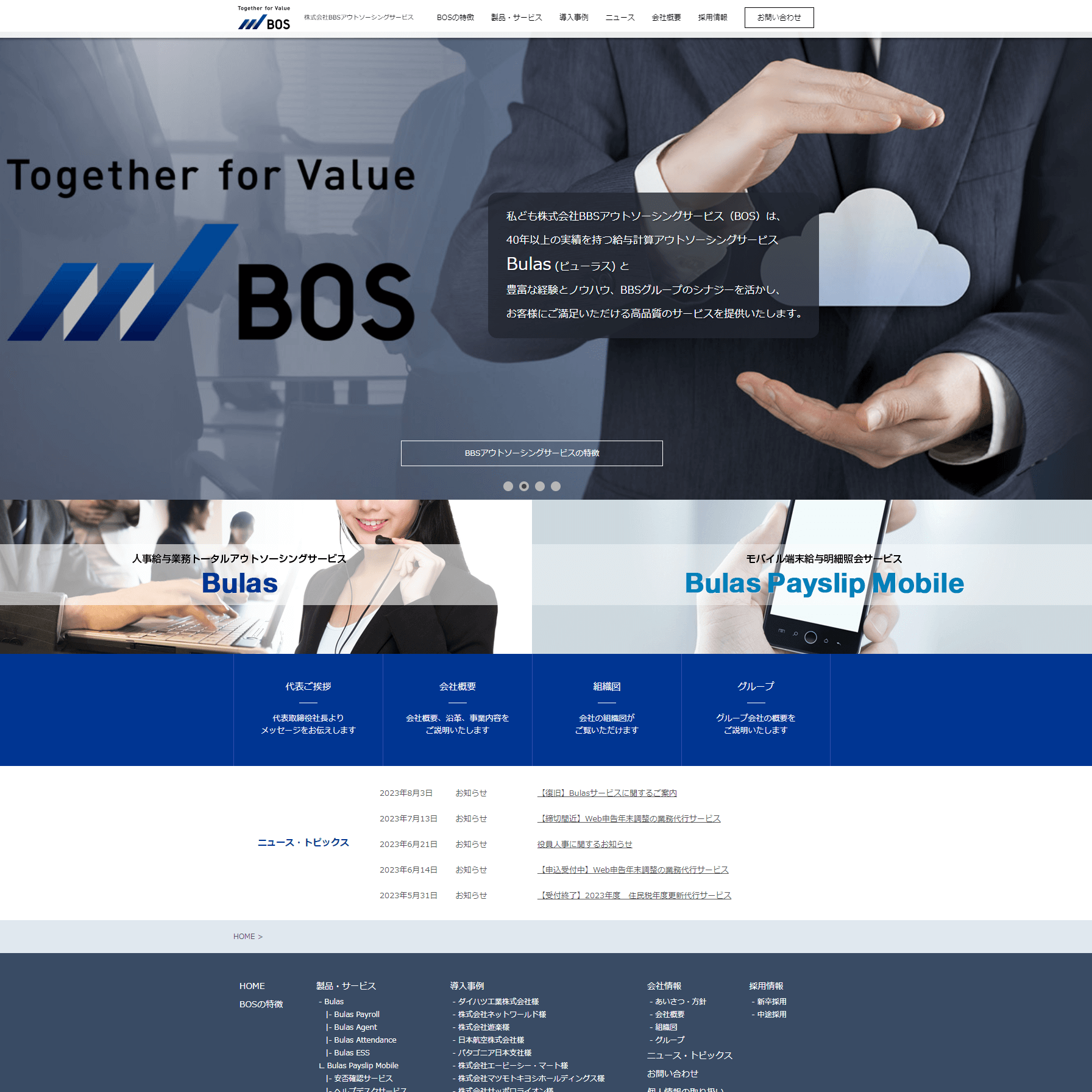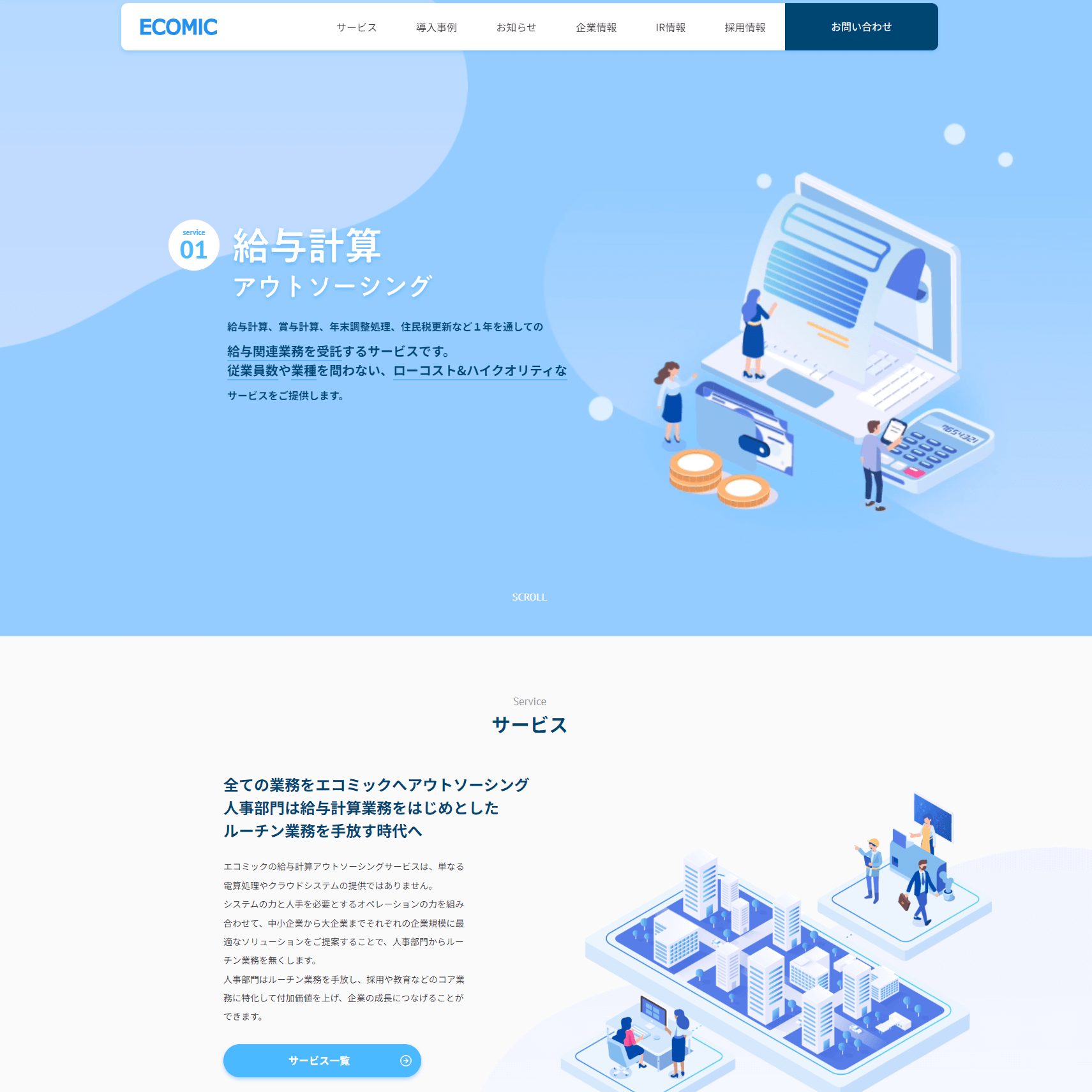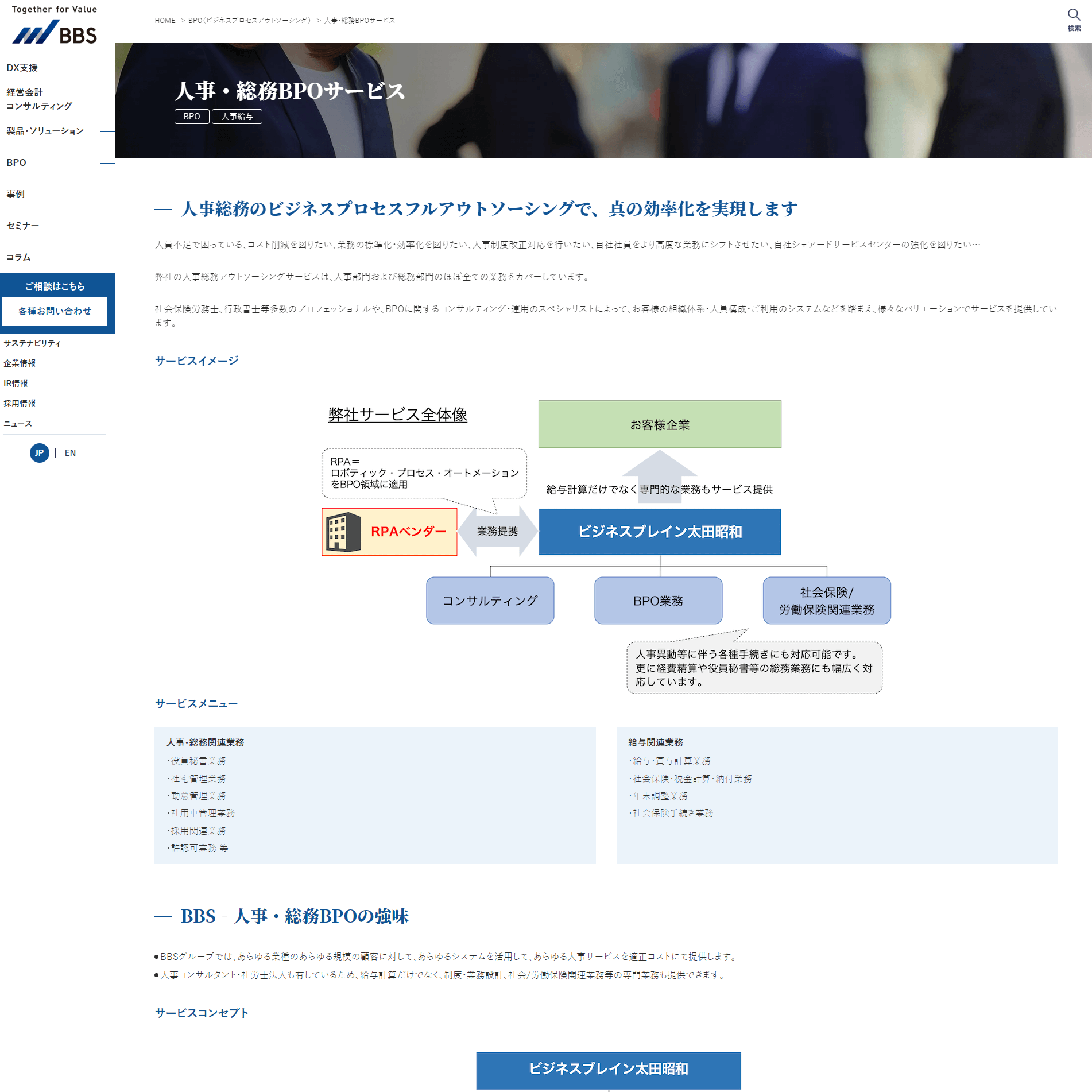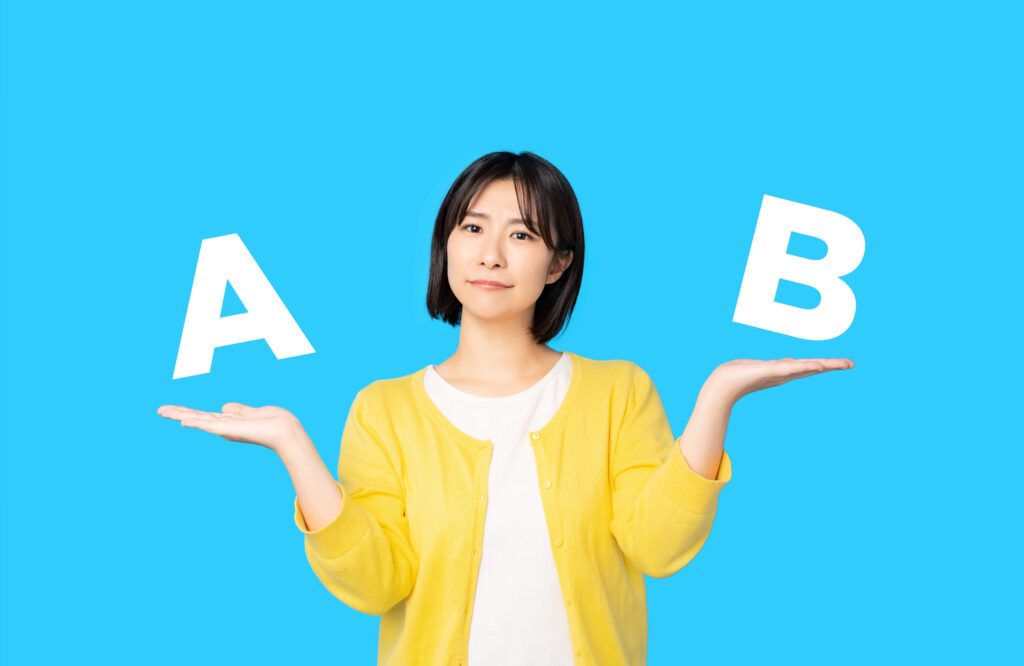
厚生年金と国民年金は、日本の公的年金制度を構成する2本の柱です。どちらも老後の生活を支える大切な制度ですが、その内容や加入対象、保険料、将来受け取れる年金額には大きな違いがあります。会社員や公務員、自営業、学生など、立場によって加入する制度が異なるため、しっかりとした理解が不可欠です。本記事では、厚生年金と国民年金の仕組みを基本からわかりやすく解説し、それぞれの違いや特徴を丁寧に比較していきます。また、制度の切り替え方法や、保険料の支払いで起こりやすい誤解などについても解説していきます。
CONTENTS
そもそも年金制度とは?
日本の年金制度は老後の生活費を支えるだけでなく、病気や障害、遺族への保障といった側面も持つ重要な社会保障制度です。その中でも「国民年金」と「厚生年金」は、すべての人が加入する仕組みになっており、職業や立場によって加入する制度が異なります。
また、年金制度は2階建て構造と呼ばれ、基本と上乗せの二層で成り立っています。まずはその全体像を理解し、自分がどの制度に該当するのか、なぜそれが必要なのかを見ていきましょう。
年金制度の2階建て構造とは
日本の公的年金制度は2階建て構造と呼ばれています。これは、すべての国民が対象となる「国民年金(1階部分)」に加え、一定の条件を満たす人が上乗せで加入する「厚生年金(2階部分)」の仕組みになっていることを意味します。
たとえば、自営業者やフリーランス、学生といった人は国民年金のみの加入ですが、会社員や公務員などは国民年金に加えて厚生年金にも自動的に加入する形になります。
国民年金と厚生年金の役割の違い
国民年金は、すべての人に最低限の生活保障を提供することを目的としています。具体的には、20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入し、定額の保険料を納付することで、老後に基礎年金として支給されるものです。
一方、厚生年金は、収入に応じた保険料を納め、その分だけ将来の年金受給額が増える仕組みになっています。これは報酬比例の考え方で、より多く働いた人、より高い給与を得た人ほど多く年金を受け取れるのが特徴です。
国民年金とは?
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入する、公的年金制度の基本となる部分です。自営業者やフリーター、学生、無職の人など、会社に勤めていない人が対象となり、保険料も定額で設定されています。
厚生年金に加入している会社員なども、この国民年金部分には重ねて加入しており、すべての国民の基礎年金といえる仕組みです。ここからは、国民年金の加入対象者の分類、保険料の金額と支払い方法、そして将来受け取れる年金額について詳しく解説します。
加入対象となる人(第1号被保険者など)
国民年金は、日本国内に住むすべての20歳以上60歳未満の人が原則として加入する基礎年金制度です。自営業者や学生、フリーターなど、会社に勤めていない人はこの制度に個人で加入する必要があり「第1号被保険者」と呼ばれます。
また、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)も、基礎年金部分として国民年金に自動的に加入しており、保険料の一部が国民年金に充てられています。さらに、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦など)は「第3号被保険者」として、保険料の負担なしで国民年金に加入する仕組みです。
保険料の金額と納付方法
国民年金の保険料は、収入に関係なく定額です。2025年度の保険料は月額16,980円(前年度より改定の可能性あり)とされており、基本的に毎月自分で納付する必要があります。
納付方法は、口座振替やクレジットカード払い、現金による納付などがあり、早めに支払う前納制度を利用すると割引が適用される場合もあります。学生や収入の少ない人向けには学生納付特例制度や免除制度も用意されており、将来の年金受給に影響を与えにくくする工夫もなされています。
受給開始年齢と年金額の目安
国民年金は、原則として65歳から老齢基礎年金として支給がはじまります。受給には最低10年間の保険料納付期間が必要で、満額(40年間=480月納付)受け取る場合、2025年度の年金額は年額約81万円(月額約6.8万円)です。
なお、65歳より早く(60歳から)または遅く(最大75歳まで)受け取る繰上げ受給、繰下げ受給の制度もあり、生活状況に応じた柔軟な選択が可能です。
厚生年金とは?
厚生年金は、おもに会社員や公務員といった給与所得者が加入する、公的年金制度の上乗せ部分にあたる制度です。国民年金と異なり、保険料が給与に応じて決まり、その分将来受け取る年金額も多くなります。
厚生年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入していることになるため、2階建ての構造で年金が支給されます。ここからは、厚生年金の加入対象者、保険料の仕組みと特徴、そして受給額の目安について解説します。
加入対象となる人(会社員・公務員など)
厚生年金の加入対象は、原則として会社や団体などに勤務する従業員です。具体的には、正社員に加え、一定の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも対象となります。
たとえば、週の労働時間が20時間以上、月収が8万8,000円以上、勤務期間が2か月超などの基準を満たすと、厚生年金への加入が義務付けられます(2024年時点の基準)。
保険料の仕組みと給与との関係
厚生年金の保険料は、国民年金と違って定額ではなく、加入者の報酬(給与・賞与)に比例して決まります。2025年度現在の保険料率は約18.3%で、このうち労使折半で支払われるため、実際に本人が負担するのは約9.15%です。
たとえば、月収30万円の会社員の場合、厚生年金の保険料は約54,900円となり、その半分の27,450円を本人が支払います。賞与(ボーナス)にも保険料がかかるため、年間の負担額は給与の金額によって大きく変動します。
受給金額の特徴と上乗せ分
厚生年金の年金額は、報酬比例部分と呼ばれ、加入期間と報酬額によって決まります。たとえば、平均月収30万円で40年間加入した場合、厚生年金の報酬比例部分だけで年額約110万円前後が支給される計算になります。
これに加えて、国民年金(老齢基礎年金)部分が支給されるため、合計で年額190万円前後になることもあります。また、厚生年金には老齢年金だけでなく、障害厚生年金や遺族厚生年金などの制度もあり、万一の際の保障も手厚くなっています。
厚生年金と国民年金の違い
厚生年金と国民年金は、どちらも日本の公的年金制度を支える重要な要素ですが、加入対象者や保険料、受給額には大きな違いがあります。国民年金はすべての国民が加入する基礎年金であり、厚生年金は会社員や公務員など、一定の条件を満たす人が加入する上乗せ部分の年金です。
ここでは、両者の違いを整理し、それぞれの特徴がどのように異なるのかを詳しく解説します。
加入条件の違い
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象です。自営業者、学生、無職の人など、職業に関係なく、すべての人が加入しなければならないのが特徴です。
これに対して、厚生年金は、おもに会社員や公務員が対象となり、給与を得て働いている人が加入します。パートタイマーやアルバイトも、一定の勤務条件を満たせば加入が義務付けられています。
保険料の支払い方法の違い
国民年金の保険料は、月々の定額で設定されています。2025年度の場合、月額1万6,980円(前年度の改定を基準に)で、収入に関係なく同一の額を納めます。
自営業者や学生、無職の人など、給与が不安定な場合でも同じ金額を納めることになります。
一方、厚生年金の保険料は、加入者の報酬(給与・賞与)に応じて計算され、保険料率は約18.3%です。
このうち、本人が負担するのは9.15%であり、残りの9.15%は会社が負担します。そのため、厚生年金は国民年金と比較して、収入が高い人ほど多くの保険料を支払い、将来受け取る年金額も多くなります。
受給額の違い
国民年金は、すべての加入者に対して基本的に同じ額の年金が支給されます。2025年度の満額受給額は年額81万円程度(月額約6.8万円)で、これが国民年金の基礎年金部分となります。
一方、厚生年金は給与に基づく報酬比例の仕組みですので、収入が高ければ高いほど受け取る年金額も増加します。モデルケースとして、月収30万円の会社員が40年間加入した場合、年額約110万円が支給され、国民年金の基礎年金部分(年額81万円)と合わせると、合計で年額190万円程度の年金を受け取ることになります。
保障内容の違い(障害年金・遺族年金など)
厚生年金には、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの保障も含まれています。障害年金は、事故や病気で働けなくなった場合に支給され、遺族年金は加入者が亡くなった場合に遺族に支給されます。
国民年金にも障害基礎年金や遺族基礎年金がありますが、その支給額は厚生年金に比べて低く、報酬比例の仕組みはありません。
厚生年金と国民年金の違いを理解しよう
厚生年金と国民年金の違いは、加入者の立場や収入によって大きく異なります。保険料や受給額、切り替えのタイミングまで理解しておくことで、ライフプランに合った選択や準備が可能になります。将来に不安を感じないためにも、自分にとって最適な年金の仕組みを今のうちから正しく理解しておきましょう。
-
 引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/
引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/