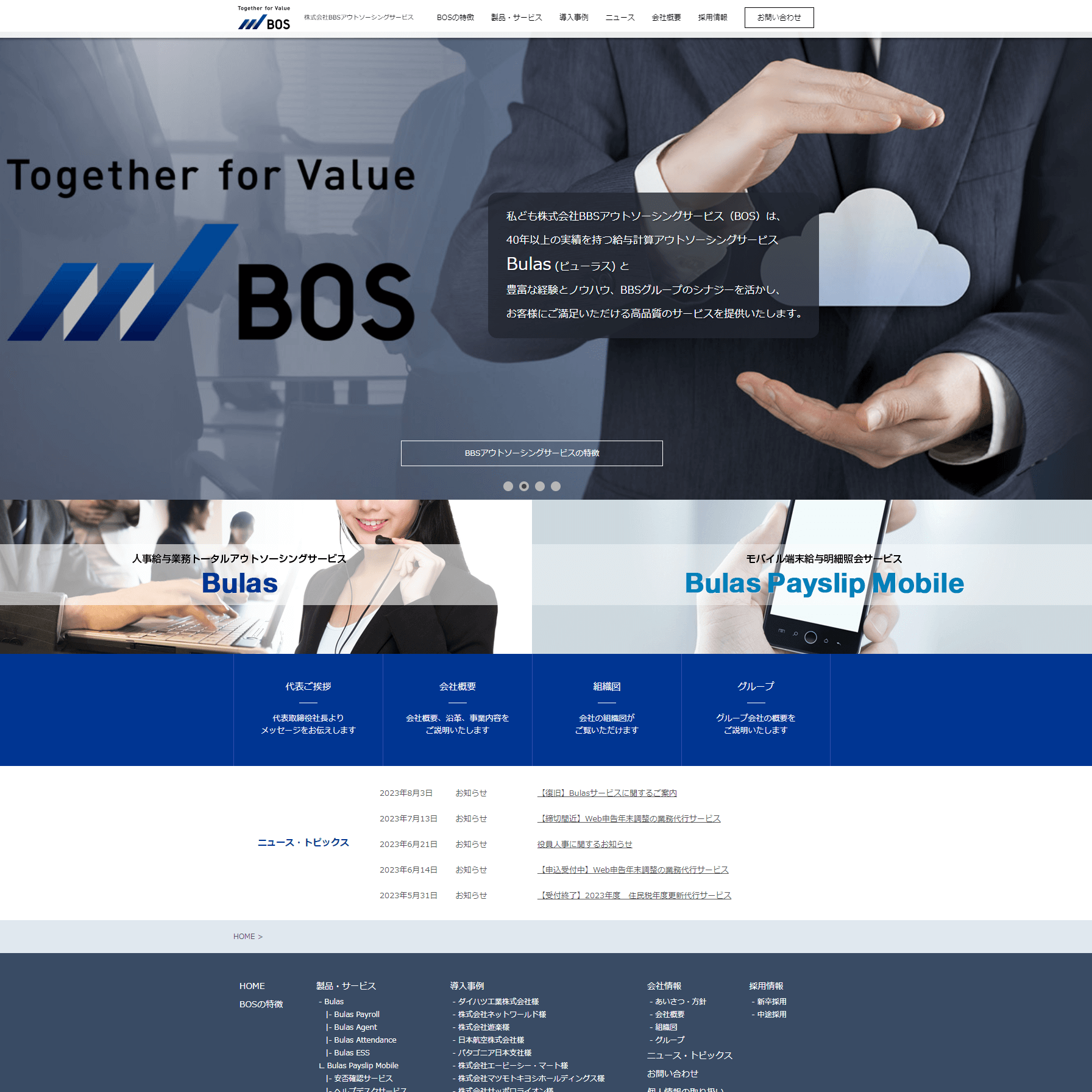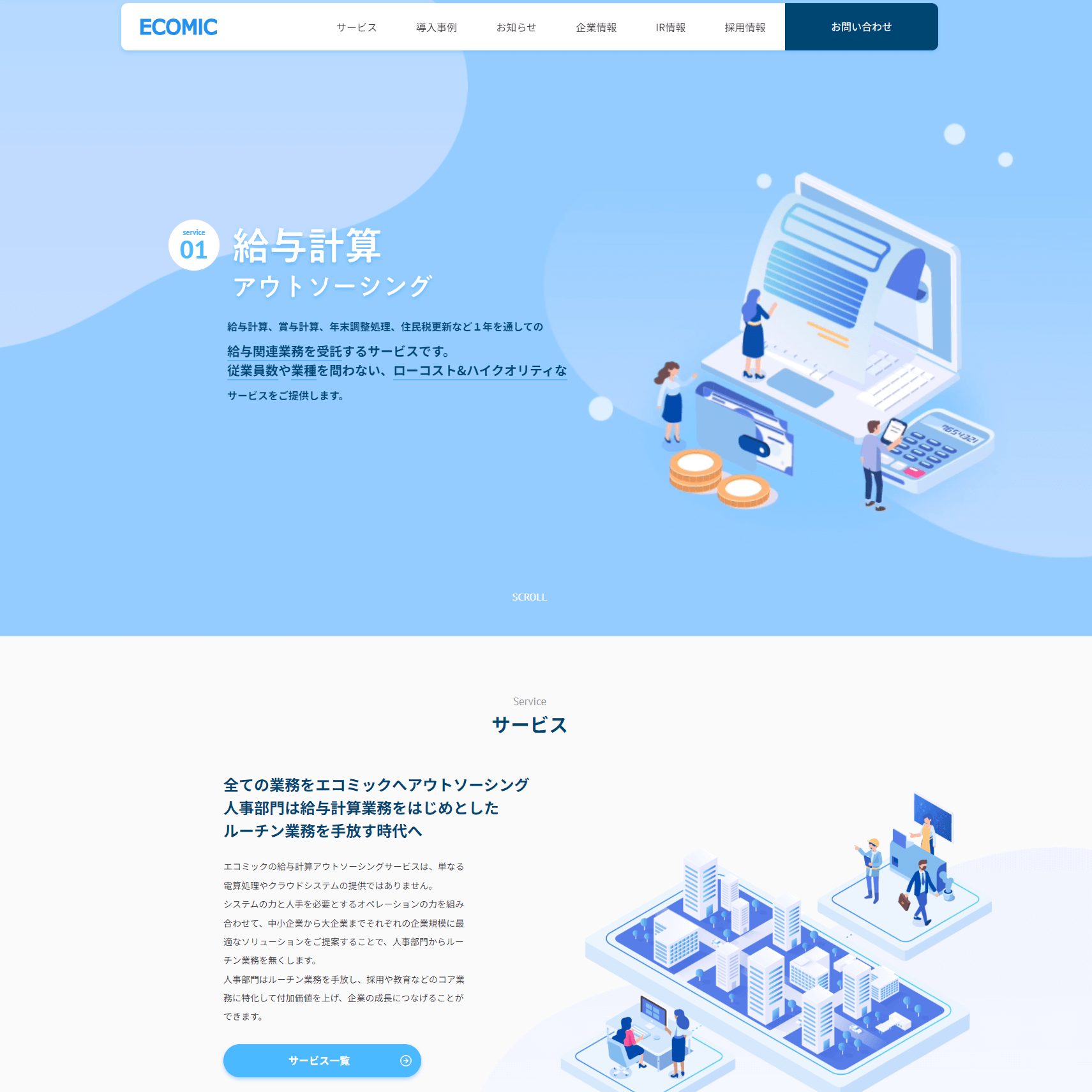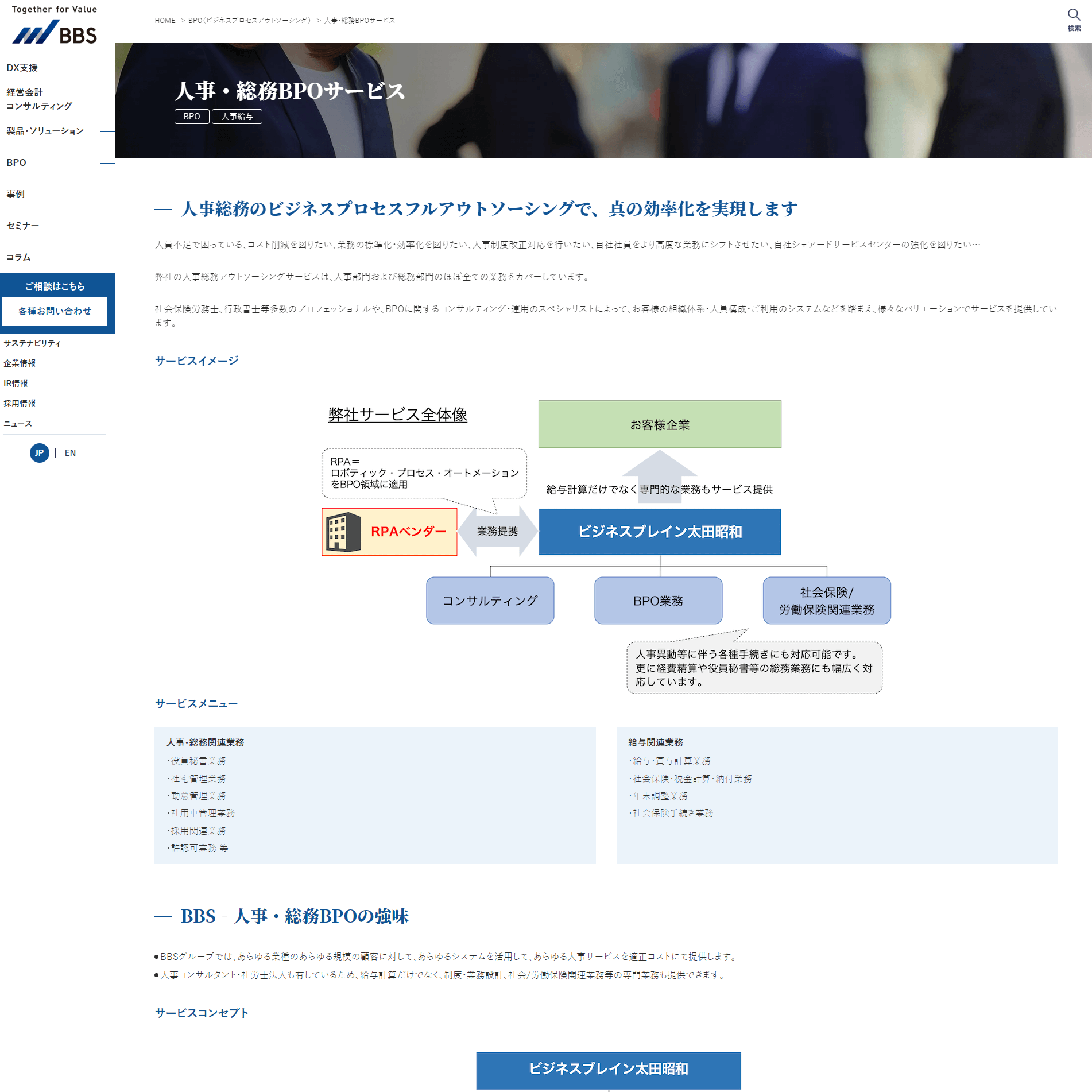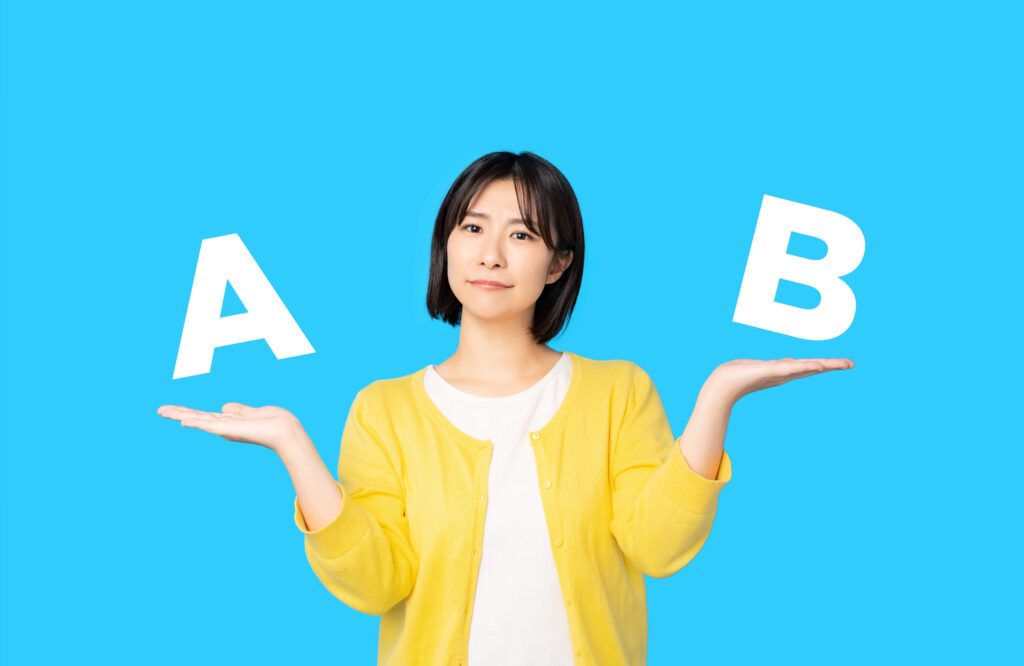雇用保険料率は、労働者と事業主が負担する重要な社会保険制度の一つです。令和7年度は、この保険料率が前年度より引き下げられることになりました。保険制度の仕組みや対象となる賃金、そして実務に与える影響などを知っておくことで、スムーズな給与計算や正確な対応が可能になります。
CONTENTS
雇用保険料や雇用保険料率とは
雇用保険は、労働者が失業したときや休業を余儀なくされたときの生活を支える制度です。働く人を支援しながら、事業主にとっても安定した雇用を保つために活用されています。ここでは、雇用保険料のしくみや保険料率について説明します。
雇用保険料の仕組み
雇用保険料は、労働者と事業主の両方が負担しています。給与総額に対して一定の割合で計算され、月ごとに給与から差し引かれる形で納付されます。保険料の徴収は事業主が行い、まとめて国に納める流れとなっています。保険料の使い道は、失業給付や育児休業給付、教育訓練給付など多岐にわたります。
雇用保険料率とは何か
雇用保険料率とは、給与に対してどのくらいの割合で保険料を計算するかを示した数値です。毎年、厚生労働省が見直しを行い、翌年度の保険料率が決定されます。保険料率は労働者と事業主で分担するため、それぞれにとっての負担割合も併せて設定されます。
保険料率はなぜ変わるのか
雇用保険料率は、制度の財政状況や失業給付の支給実績などをもとに見直されます。雇用情勢が改善し、給付の必要が少なくなると、料率が引き下げられることがあります。反対に、失業者が増加したり、支出が多くなったりすると、料率が上がる場合もあります。年度ごとに状況が変わるため、毎年の確認が必要です。
令和7年度雇用保険料率は引き下げ
令和7年4月から令和8年3月末までの雇用保険料率が、前年度よりも引き下げられることが決まりました。労働者と事業主の両方が少しずつ軽減される内容となっています。ここでは、その変更内容と背景を詳しく紹介します。
料率の引き下げ内容
令和7年度の雇用保険料率は、全体で0.1%引き下げられました。具体的には、労働者負担が0.9%から0.85%に、事業主負担が0.6%から0.55%になります。合計で1.45%となり、前年度の1.55%から低くなります。この料率はすべての事業に共通して適用され、給与計算にも直接影響します。
見直しの背景
保険料率が引き下げられた背景には、雇用保険財政の安定があります。近年、失業給付などの支出が減少しており、財政に余裕が生まれてきました。
厚生労働省では、こうした状況をふまえ、労使双方の負担軽減を目的として料率の引き下げを決定しました。保険制度としての持続可能性が保たれている中での措置といえます。
給与計算での留意点
新しい保険料率は令和7年4月1日以降に支払われる給与から適用されます。給与計算を行う事業主や担当者は、保険料率を正しく変更しておく必要があります。
間違った料率で計算すると、従業員からの信頼を失うだけでなく、差額の再計算や納付手続きにも手間がかかります。給与ソフトの設定や委託先への確認など、事前の準備が重要です。
雇用保険料率が変わるとある影響
雇用保険料率は、毎年見直される可能性があります。変更があった場合、労働者にも事業主にもさまざまな影響が生じます。ここでは、給与計算の現場や経営への影響を中心に、雇用保険料率の変化がもたらす主なポイントを解説します。
給与計算業務の見直しが必要になる
雇用保険料率が変更された場合、給与計算の設定を正しく変更することが必要になります。とくに、給与計算ソフトを使用している場合は、料率の更新が反映されているかどうかを確認しなければなりません。反映が遅れた場合、保険料の過不足が発生し、再計算や従業員への説明対応が発生するおそれがあります。
外部へ給与計算を委託している場合でも安心はできません。アウトソーシング先が制度変更に対応できているかを確認し、必要に応じて情報提供や設定変更の依頼を行う必要があります。年度の切り替え時期にはとくに注意が求められます。
企業の人件費に直接影響する
雇用保険料率の変更は、企業にとって人件費の増減に直結します。たとえば、料率が引き上げられた場合は、それだけで毎月の人件費が増えます。逆に、今回のように引き下げられた場合でも、影響は少なくないため、年間でのコスト変化を把握しておくことが重要です。
とくに複数名の従業員を抱える中小企業にとっては、保険料の負担が少しでも軽減されることで、経費の見直しや別の投資への資金確保にもつながる可能性があります。ただし、長期的な視点で見ると保険料率は将来的に再び上がることもあるため、一定の予算余力を持っておくことが望ましいです。
労働者の手取りにも変化が出る
雇用保険料は、労働者の給与からも差し引かれる項目です。そのため、料率の変更は直接的に手取り額の増減につながります。今回のように労働者負担が0.05%下がった場合でも、毎月の給与に多少の変化が出ることになります。
金額としてはわずかでも、従業員にとっては「保険料が変わったのに説明がなかった」と不安になる要因になることもあります。給与明細への反映はもちろんのこと、企業として事前に簡単な説明を行っておくと、信頼性の維持にもつながります。
法改正情報の管理と対応力が求められる
雇用保険料率のような制度変更は、年に一度は発生する可能性があります。その都度、制度の内容を確認し、社内で共有する体制が必要になります。情報をいち早くキャッチし、必要な処理を社内外で進めていく対応力が求められます。
給与計算の担当者や経理部門が中心になりますが、外部委託している場合でも、最終的な責任は事業主側にあります。厚生労働省や信頼できる会計ソフト会社などが発信する情報を定期的にチェックしておくことが、ミスやトラブルの防止につながります。
雇用保険料率の計算方法
雇用保険料は、毎月の給与や賞与をもとに計算されます。ただし、すべての支払いが対象になるわけではなく、計算方法や対象賃金の範囲には決まりがあります。ここでは、基本的な計算方法と、保険料算出の対象となる賃金・ならない賃金について解説します。
雇用保険料率の基本的な計算方法
雇用保険料は「総支給額×保険料率」で算出します。たとえば令和7年度の料率は1.45%で、労働者が0.85%、事業主が0.60%を負担します。月給が30万円の場合、労働者は2550円、事業主は1800円の保険料を支払うことになります。
給与計算ではこの金額をもとに、月ごとの控除処理や納付処理が必要となります。賞与なども含めた支給額すべてに対して保険料を計算する点が特徴です。
保険料率の対象となる賃金
雇用保険料の対象になる賃金には、基本給のほかに各種手当や残業代、通勤手当、住宅手当、皆勤手当などがあります。定期的に支払われるもの、業務に関連する報酬は原則として対象に含まれます。
さらに、賞与や決算手当といった臨時的な支給も対象です。現金ではなく現物で支給された食事や交通費補助も、評価額に換算して対象に含まれる場合があります。
保険料率の対象とならない賃金
一方で、雇用保険料の対象外となる賃金もあります。たとえば、慶弔見舞金、退職金、出張旅費、制服や備品の支給などは対象外です。また、労働に直接関係しない贈答品や表彰記念品なども含まれません。
これらは福利厚生や補助の位置づけであるため、保険料の計算からは除かれます。対象外の支払いが多くなると、保険料額も抑えられる傾向にありますが、制度上の判断基準に従う必要があります。
まとめ
令和7年度の雇用保険料率は、労働者・事業主ともに0.05%ずつ負担が軽減される形で見直されました。保険料率は毎年の雇用情勢や財政状況に応じて調整されるため、制度の仕組みや変更の背景を正しく理解することが大切です。また、給与計算に直接関わるため、対象となる賃金や対象外の賃金も確認しておきましょう。料率の改定時には、社内での設定変更や外部委託先との連携を徹底し、正確な処理を心がけることが必要です。
-
 引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/
引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/