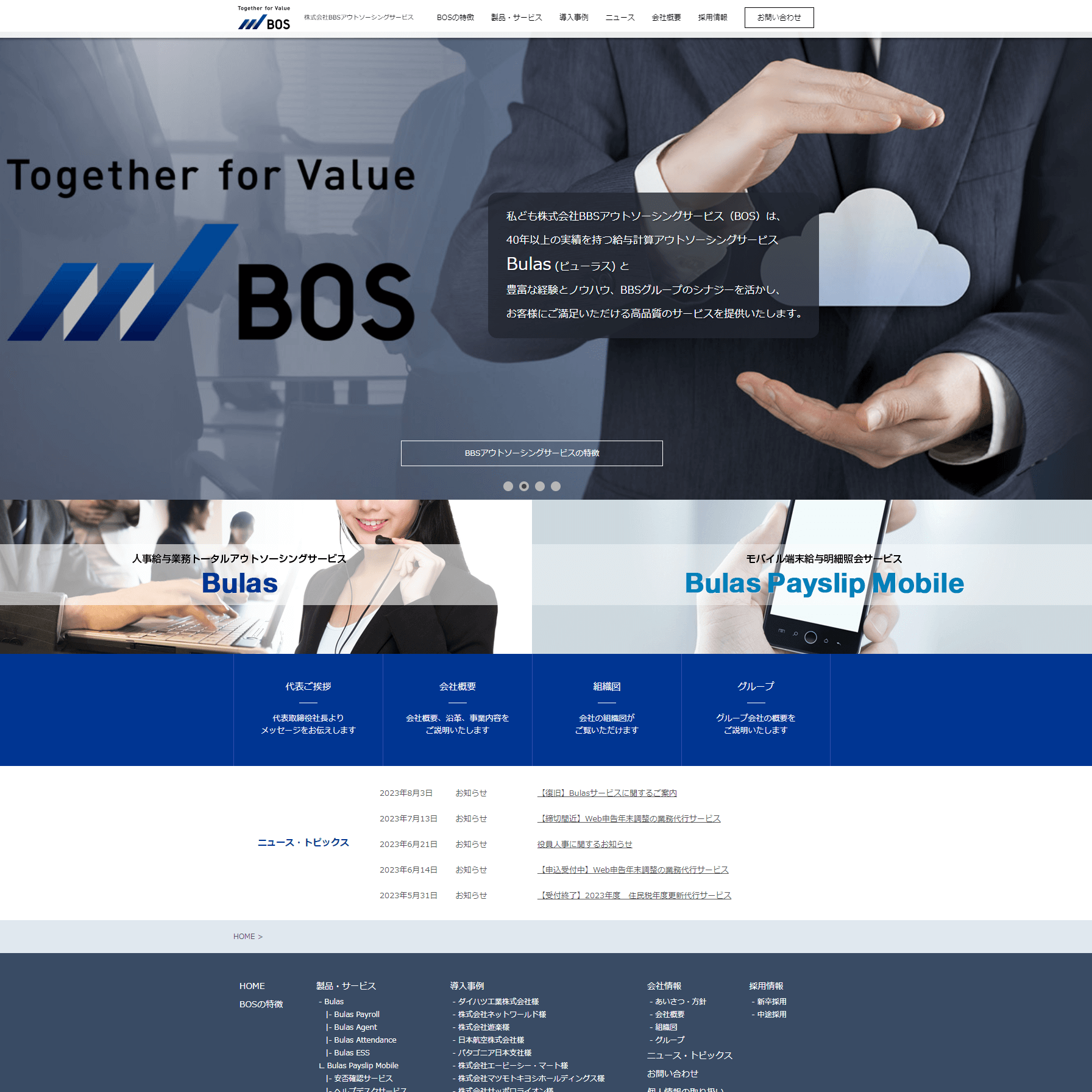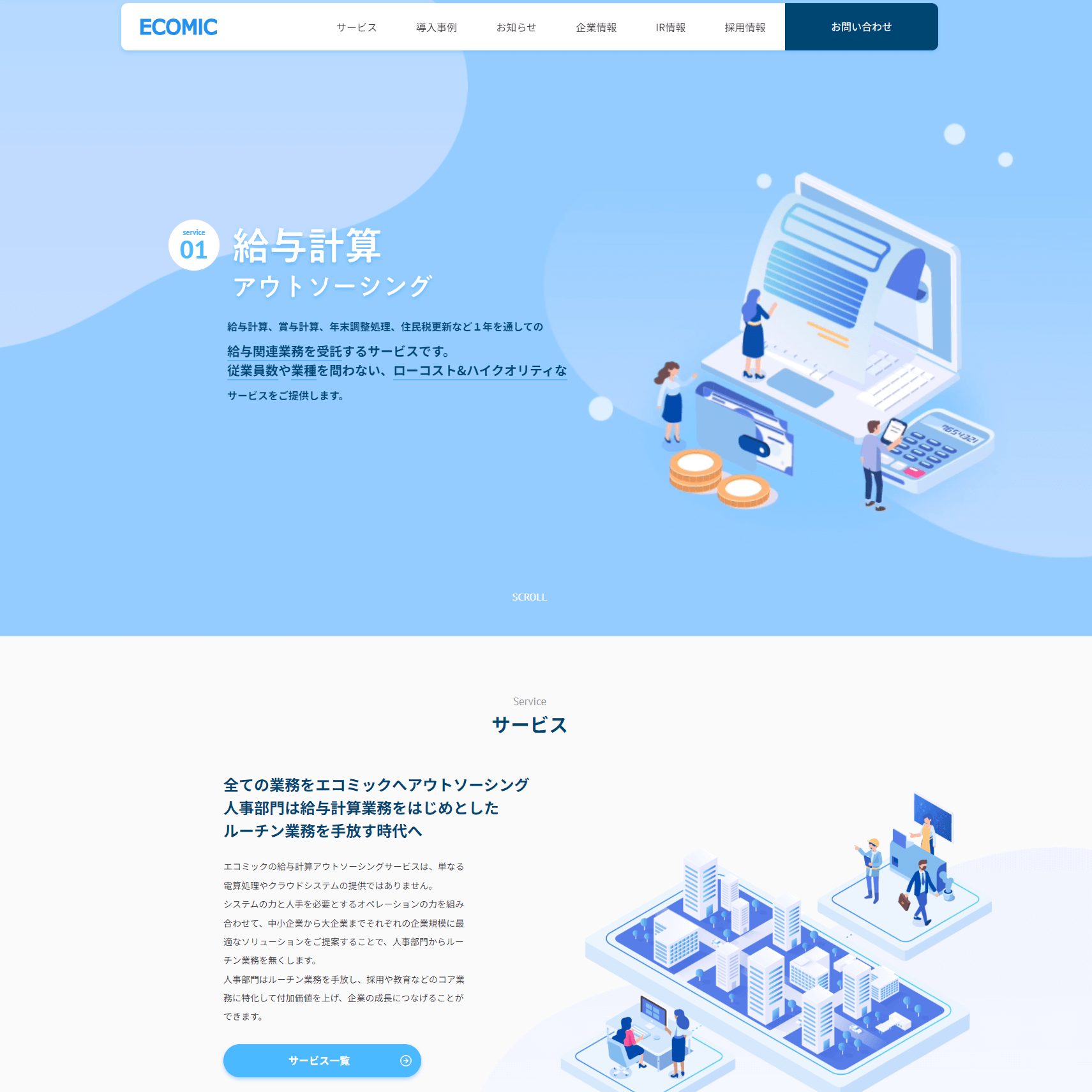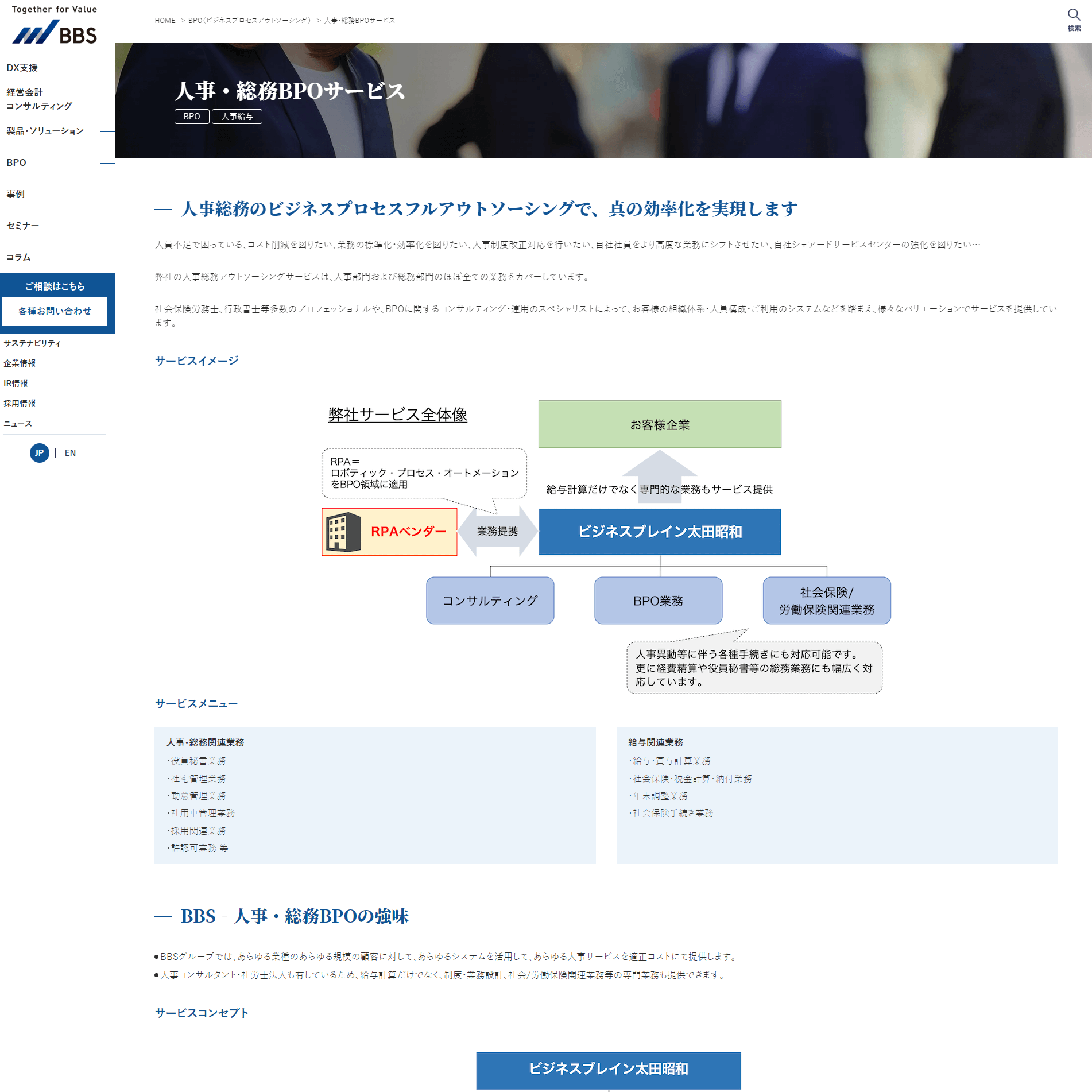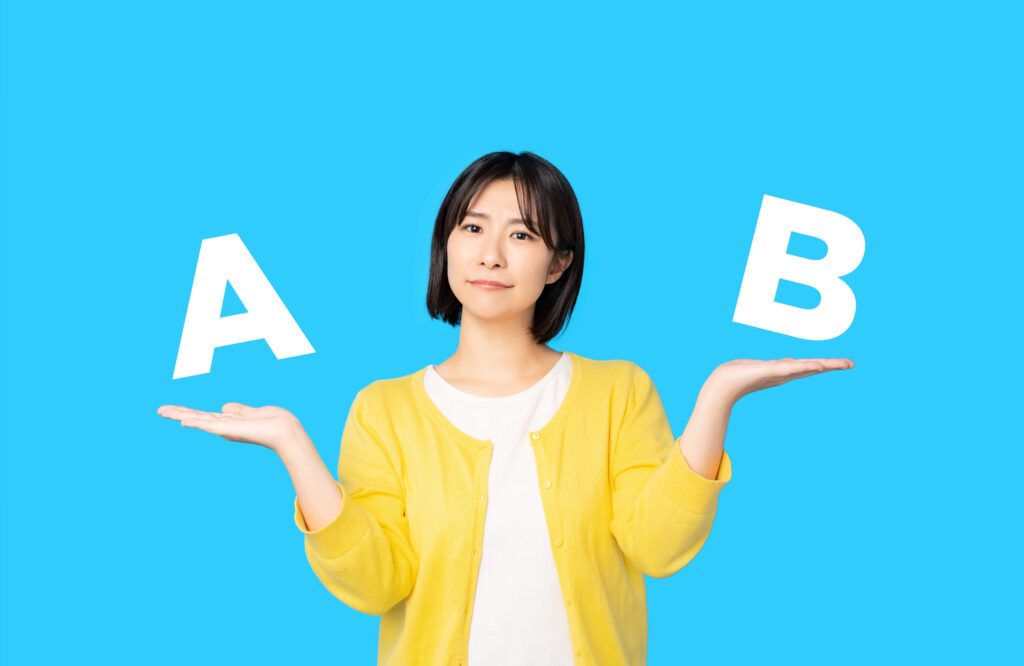もらっている報酬が大きく変わった場合は申請してください。ただし、保険にかかわる内容は確認する内容や手続きで記入する項目が多いため、情報の間違いがないか慎重に書類を作成します。そこで今回は保険料の改定について詳しく説明します。ぜひ参考にしてください。
CONTENTS
随時改定とは
従業員の報酬額が大幅に変わると、その実情に合わせて保険料を調整する申請が求められます。
毎年決められた期間のみに実施される方法では、カバーしきれないイレギュラーな昇給・減給に対応し、もらっている報酬を最新の情報へ更新する役割を担っています。
正しい理解と迅速な対応が、企業と従業員双方の負担を防ぐカギです。
随時改定で用いる基準額
厚生年金や健康保険の金額を決めるには報酬をちょうどよいところで区切るのです。
多くの保険では、最小の1からカウントし、最大値が32や50といった数字で分けて管理します。割り振られる数値が高くなるほど支払う金額も増える仕組みです。
給与が増えれば等級は上に移り、減れば下がるため、実態とかけ離れた等級のまま放置するのはよくありません。
スムーズに申請するために、自分が受け取る給与を常に把握しておき、必要であれば信頼できる部署や機関に確認しておくといいでしょう。
定時決定とは
毎年9月に従業員の報酬額を評価する仕組みです。会社は7月初日の時点で働いている人たちへ支払った4・5・6月から基準額を出します。
7月中に、専用の書類を作成して提出すれば申請は完了です。そうすると、各保険組織から基準額の通知が会社宛てに送られてきます。内容は必ず確認しておきましょう。
しかし、この期間以外に生じた大幅な昇給や減給は反映されません。報酬が変わったときに申請すると、そのギャップを埋めるために用意されました。年1回の決定と組み合わせることで、支払う金額を常に適正な水準へ保つことが可能になります。
ちなみに、届け出た年の9月から、来年の8月まで有効です。
控除される時期
従業員の給与内容に関する変更申請後、次の基準額に切り替わる期間は、報酬が変わった月からカウントして4か月後です。
ただし、企業によっては控除の時期が異なります。
控除は給与システムに関連して翌月が多いですが、すぐ切り替えられる当月を採用しているところもあります。
また、退職といった特殊な場合では、翌月が基本の企業でも当月から切り替わる処置をしている場合もあり、確認が必要です。詳細は勤めている企業に聞いておきましょう。
まとめると、控除する時期が当月の会社なら、受け取る報酬が変わった月から4か月目に切り替わります。翌月なら控除は5か月目からです。
具体的なケースで考えていきましょう。給与が翌月払い、連動して控除の切り替えも翌月として説明します。
4月中に給与が大きく変わったなら、5月に4月勤務分の給与を受け取り、8月まで以前の状態を維持するわけです。
そして、9月から新しいものに切り替わります。5・6・7月の3か月間で得た報酬の平均が次の指標になります。
つまり、報酬が変わった月から5か月後に控除内容が切り替わるわけです。
翌月払いの場合、控除が有効になる時期にズレが発生することを知っておきましょう。
また、申請しても認められて有効になるまで期間を要します。
随時改定の条件
固定給の金額が変わり、給与と関係する日数が指定された日数を超えると申請が必要です。
日数は詳細まで指定されており、自分の契約内容によって数え方が違うため、確認しておきましょう。
日数の計算方法は複雑で、心配なら専門家や担当部署の人に相談してください。
賃金が変わる
給与や手当といった、受け取る金額が一定のものが変わったとき、条件を満たします。
具体的には昇給・減給したときや、報酬に関連する単価が変わった場合、請負給を計算するのに用いる単価や比率が変わったケースが該当します。
手当では、項目の追加や削除、変更が当てはまります。
個人の業績や時間で金額が変わってしまう残業代は対象外です。
給与・手当など、従業員が受け取れる内容が変わったとき、条件がクリアされます。
給料が発生する日数が規定以上
従業員の給料が変わった月以降の3か月間、給与と関係する日が17日以上なら条件クリアです。
月末を締め日にして、翌月25日に働いた分の給与を受け取れる会社を具体例に説明します。
この企業では、1月の働いた分を受け取るのは2月です。つまり、1月に給与内容が変わると、1月ではなく2月の受け取る報酬が変化します。
報酬が変わった給与をもらう月からカウントして3か月間で給与と関係する日数がそれぞれ17日以上あれば条件クリアです。
給与計算の対象日数を確定する方法は3つです。欠勤の扱いが大きく異なるため、注意しましょう。
日給月給制は、毎月の給与が決められており、従業員が会社の仕事に参加していない日数が引かれていくものです。
企業が定めた日数から従業員が出勤していない日数を引いて給料が発生する日を数えます。
完全月給制は、シンプルな計算で済みます。受け取れる給与があらかじめ決まっている契約で、出社していない日数による減額はありません。対象期間中は、欠勤も有効日に数えます。
時給・日給制は、仕事に参加している時間で給与が発生する雇用形態です。働いた日数と有給休暇が有効な日数として扱われます。
つまり、給与形態によって算出方法が大きく異なるため、自社の契約内容を把握することが大切です。
等級大きく変わったとき
固定給が変わる前の基準額と、変わった月から3か月間に受け取った給与の平均から計算された金額に大きな変化が発生したとき、条件を満たします。
等級は保険機関が公式サイトや窓口で提供している資料で確認可能です。等級が大きく変わったら申請します。
ただし、昇給・減給それぞれが枠の上限・下限になるケースでは、大きく変わっていなくても申請が必要です。
厚生年金の場合で説明します。現在31等級なら、報酬が増えたら上限枠の32等級に移行するため、申請します。
また、下限枠の1にいる状態で、1つ上に移った際も申請します。
基本的に等級が大きく変わったら申請します。しかし、等級表の昇給・減給項目の上限枠・下限枠に該当するなら、1つ変わるだけでも申請が必要です。
改定の申請をしなくてよい場合
報酬をもらっていても、以下の人は申請しなくてよいと定められています。
休職中で規定を活用している人は、除外です。
基準額に大きな差が発生しても、固定部分の賃金が増えても残業部分が減少しているなら必要ありません。また固定部分の賃金が減って、残業が増加した結果変わったものは除きます。
とはいえ、条件が複雑なため自分が対象になるかどうかは信頼できる人に相談しておくといいでしょう。
手続きの方法
申請する方法は2つあります。
専用の用紙に記入して指定された施設か年金事務所へ提出する方法と電子申請です。
今回は用紙に記入する方法を紹介します。
年金機構の公式サイトから用紙をダウンロードしてください。郵送するときは添付書類を基本的に入れません。
提出者記入欄に、保険の申請をした際にもらった事務所整理番号を記入します。各保険の通知書で確認可能です。数字とカナで構成されています。
年金整理番号も書きます。これは保険を受ける資格を得たときにもらえる番号です。送付される保険の通知書で確認できます。
保険に入っている人の名前・生年月日を記入してください。
改定年月は少し複雑です。給与が変わってからカウントして4か月目の月を書きます。
以前の基準額を記入しましょう。最小単位は千円です。また、従前改定月は変わる前の基準額が有効になった年月です。
昇給か減給かどちらかを選択します。
給与の未払い分があるなら、遡及支払額という項目に書きます。差額を割り出して書いてください。
受け取る給与内容が変わった月からカウントして3か月分の月を支払月に書きます。
休養が発生する日数である基礎日数を記入すれば、提出書類は完成です。
まとめ
もらっている固定給が大きく変わり、日数の条件をクリアした状態なら申請が必要です。報酬が上がったり、下がったときの保険料は変わります。しかし、定期的な評価では反映までに長い時間が必要になります。その差をカバーする役目が改定です。詳細が決められています。自分の状況を分析しながら、表を駆使して判断しましょう。自分の状況では、申請すべきなのか知識を身につけておけばスムーズにできるはずです。今回の記事を参考に、改定の知識を身につけましょう。わからないことがあったら、信頼できる人のアドバイスを受けてください。
-
 引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/
引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/