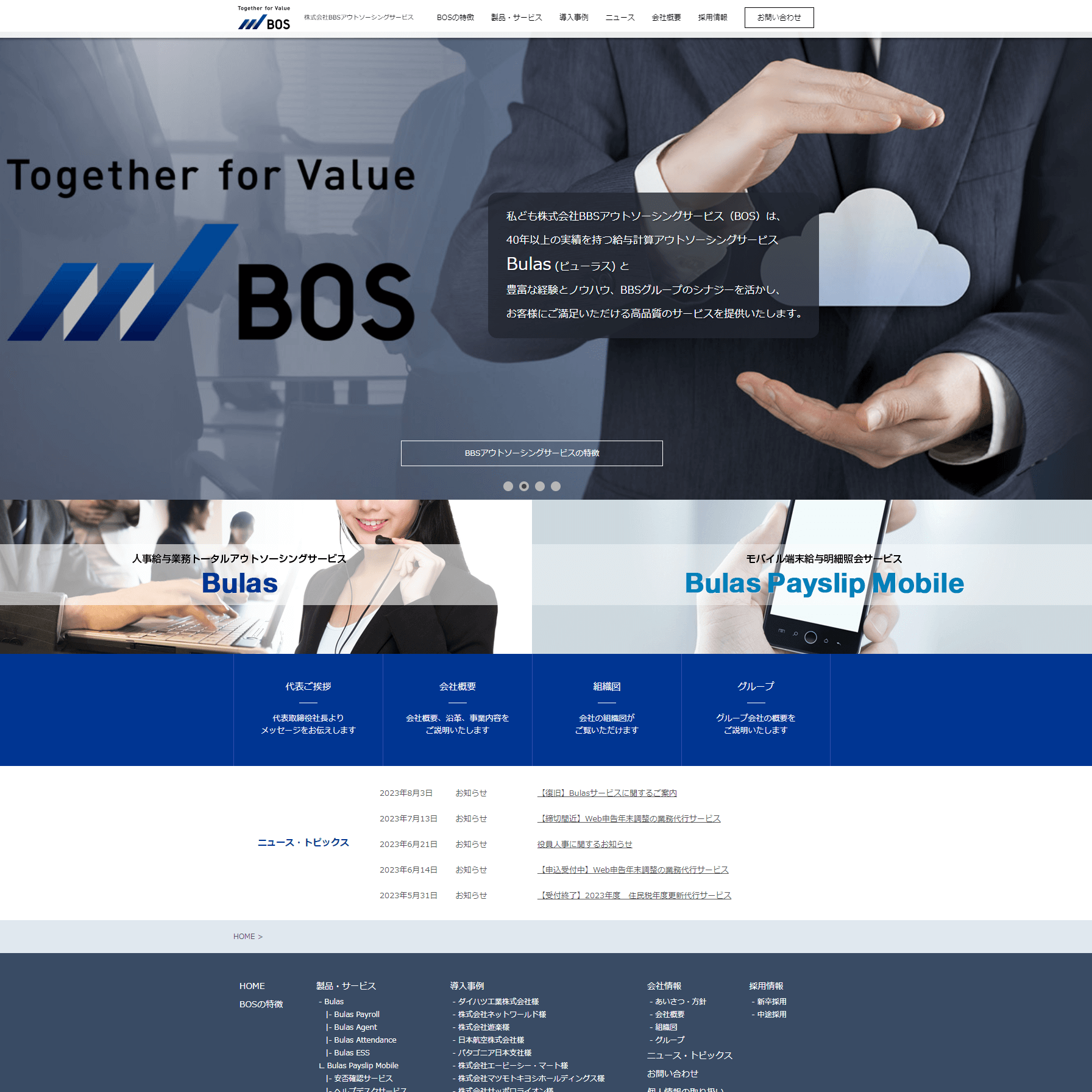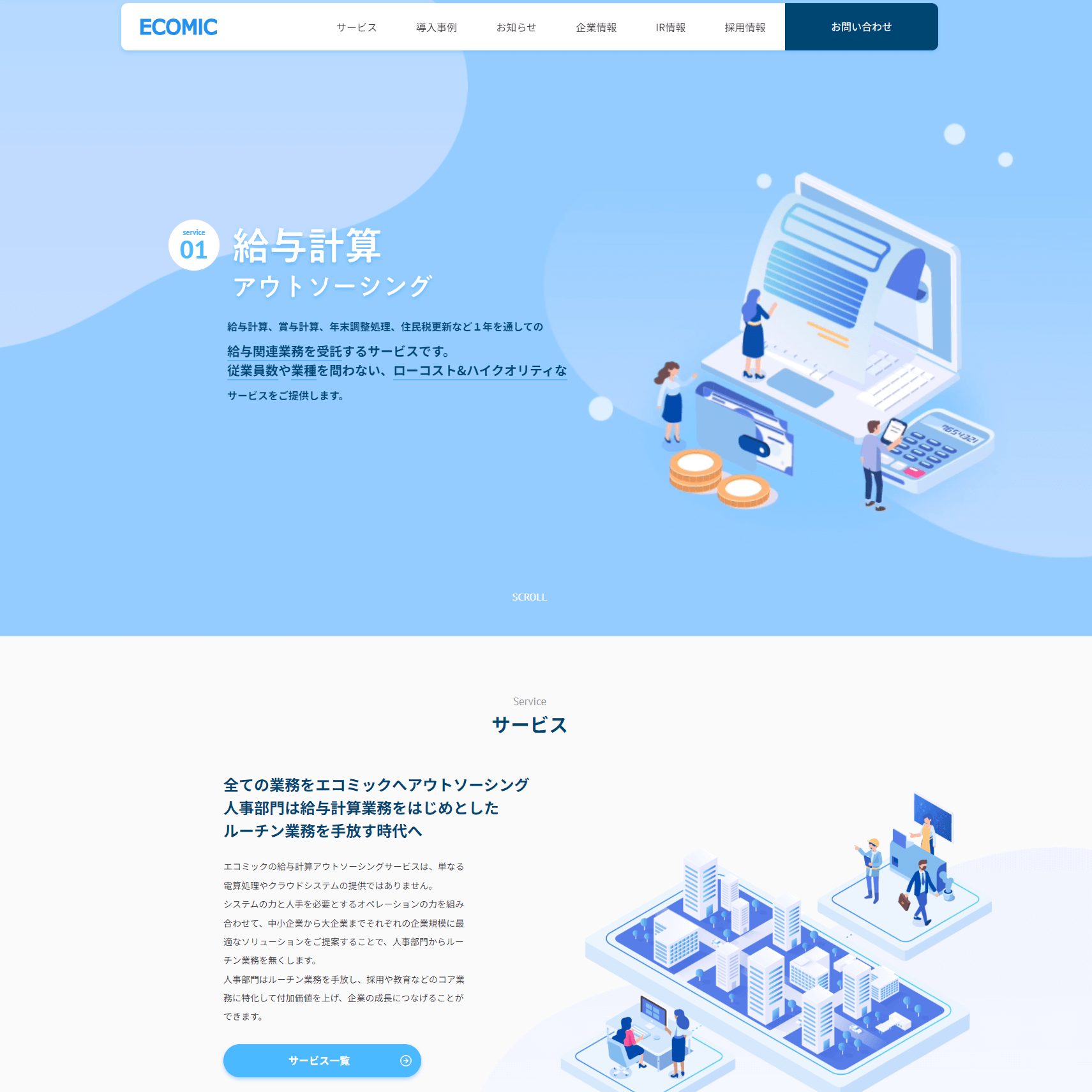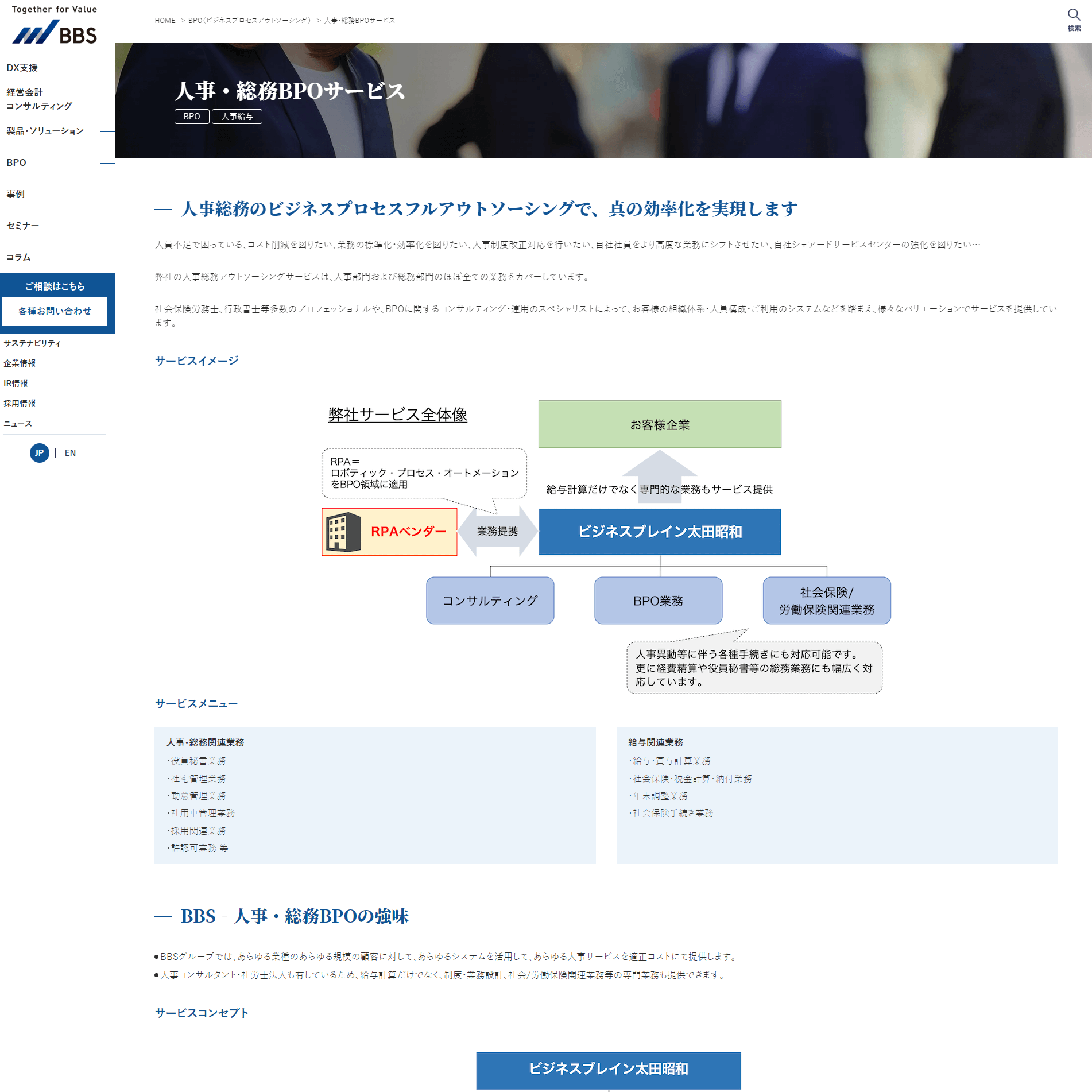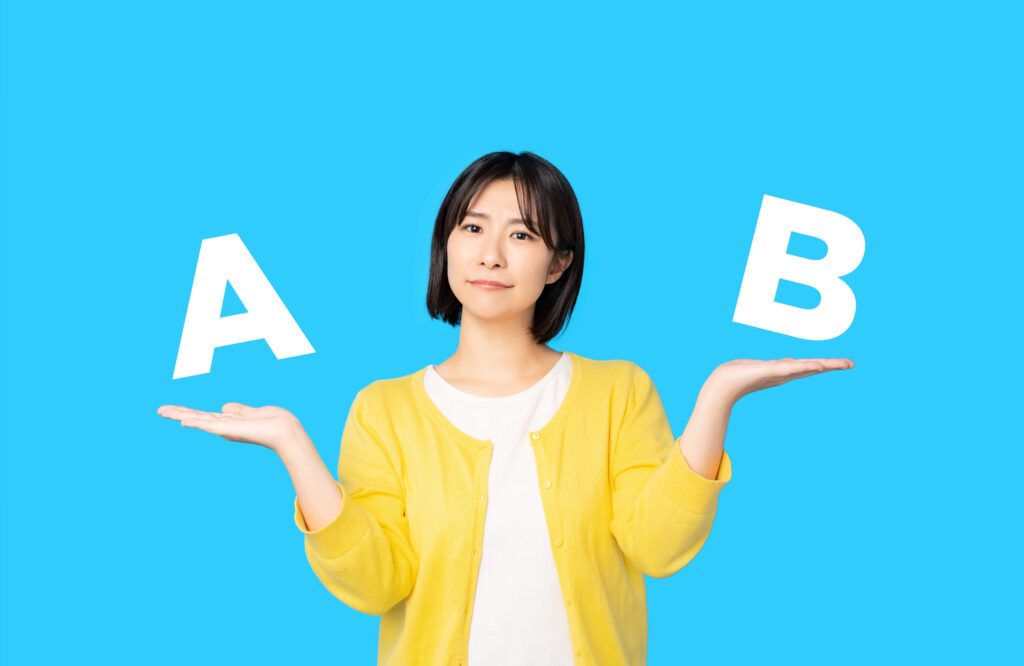企業が従業員に対して12月31日までの1年間に支払った給与で源泉徴収した税額と、実際に徴収しなければいけない税額を調整する手続きが、年末調整です。従業員に給与を支払っている事業者が主体的にする手続きであり、適切な対象者に対して実施しなければいけません。書類が複雑で戸惑うこともあるため、正しい知識を身に付け、期日に間に合うよう準備しましょう。今回は年末調整に必要な書類と書き方について、解説します。
CONTENTS
年末調整をしなければいけない対象者
会社に所属していて、給与を支払っている従業員が主な対象者です。手続きをする時期に所属していない人に対しても、年末調整をしなければいけないパターンもあるため、詳しく解説します。
給与を支払う従業員
1月1日~12月31日までの1年間、継続して会社で働く社員は年末調整の対象者です。1年間は所属していなくても、年内に入社して12月31日まで働いている方も対象となるため、確認しておきましょう。
注目するポイントとしては「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方が、当てはまるということです。途中入社の方は最初の給与が支払われる前に提出しており、当初提出されている申告書の内容から住所や扶養親族の変更がないかもあわせてチェックしておくとよいでしょう。
年末以外に手続きが必要なケース
すでに退職していても年末調整の手続きが必要な方もいるため、忘れないようにしましょう。1年間の途中で退職した場合、年末ではなく年の途中で手続きをします。
1年の途中で申告手続きが必要な状況は5つあり、1つ目は死亡により退職した方です。2つ目は著しい心身の障害により退職し、年内に再就職も見込まれない場合も対象となります。
3つ目は退職が決まっているものの、12月に給与や賞与をもらってから退職するケースです。4つ目はパートやアルバイト従業員で、年末までにもらう給与が123万円以下の方が対象ですが、退職後にほかの勤務先から給与を得る予定のある場合は、対象外のため手続きの必要はありません。
5つ目のケースは退職はしていなくても、海外支店に転勤となり非居住者になった方は、年の途中で年末調整の手続きが必要なため、気を付けましょう。
手続きの必要がない従業員
1年を通して企業に勤務している方でも、年末調整の対象とならないケースもあるため、確認が必要です。対象外となるケースは2つあり、1つ目は年間の給与総額が2,000万円を超える方は年末調整の対象ではありません。
2つ目はその年の給与にかかる所得税や復興特別所得税の源泉徴収で、徴収猶予や還付を受けた方です。会社に在籍していても手続きの対象外となるため、覚えておくとよいでしょう。
事業者が主体となる年末調整の対象ではなくても、個人で確定申告をしなければいけないというケースもございます。
年末調整に必要な書類
必ず提出しなければならない書類は、主に3点です。ほかに控除を受ける必要がある対象者だけ、個別で用意する書類もあるため、必要に応じた準備をしましょう。
必ず提出する書類
年末調整の手続きをする全ての方が提出しなければいけない書類の1点目は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。基本的な納税者の情報や配偶者、扶養親族について記載します。
2点目は「給与所得者の保険料控除申告書」という、保険料に関する情報を記入する書類です。毎月の給与から控除される保険料とは、記入する内容が異なるという所に注意しましょう。
3点目は「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類が必要です。基礎控除や配偶者控除、特定親族特別控除や所得金額調整控除などを受けるために、欠かせません。
3つの書類を基本的に提出しますが、受ける控除の内容によって、あわせて提出しなければいけない資料もあるため、確認が必要です。
該当する人が準備する書類
住宅の購入や増改築などで住宅ローンを支払っているという方を対象とした、住宅借入金等特別控除という制度があります。初年度は個別で申告をして適用された方が、翌年から年末調整で申告する際、住宅借入金等特別控除申告書を提出します。
住宅借入金等特別控除を申告する方は、借入金の年末残高等証明書のデータや書面を用意しましょう。ほかの控除を受ける方も、個別で準備する書類がいくつかあります。
生命保険や地震保険に加入している方は、保険会社から送られてくる控除証明に必要な書類やデータを忘れないようにしましょう。確定拠出年金の掛け金や国民年金を支払ったという証明書類も、控除の手続きに必要です。
配偶者特別控除を受ける方は、パートナーの所得額がわかる源泉徴収票等を用意しておきましょう。必須ではない場合もございますが、あらかじめ控除について必要な手続きや準備しておいた方がよい書類を、本人に知らせておくと安心です。
提出書類の詳しい書き方
申告手続きを滞りなく進めるためにも、的確な書類の記入が欠かせません。必ず提出する書類の書き方について、紹介してまいります。
所得税の控除申告に欠かせない書類
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、申告者の氏名や住所、生年月日と会社名などを記入します。源泉控除対象配偶者がいる場合は、配偶者の名前と個人番号や年内所得の見積額も必要です。
配偶者がいても、源泉控除対象ではないというときは、配偶者の有無で「有」に丸をつけるだけで、配偶者の氏名欄は空白で問題ありません。ほかにも控除対象の親族については、それぞれの記入欄に氏名等の情報を記入します。
16歳未満の扶養親族は、所得税の控除には関わりませんが、住民税の計算対象にはなるため、忘れずに記入することが大切です。記入欄が控除の対象により異なるため、事業者は従業員に合わせて的確に答えられるようにしましょう。
保険料控除に関する書類
生命保険等の保険料控除を受ける方は「給与所得者の保険料控除申告書」に、必要な情報を記入しなければいけません。基本的な氏名や住所とあわせて、加入している保険の内容が必要です。
毎月の給与から引かれている健康保険料や厚生年金保険料などは、記入しなくてもよいため、従業員個人が加入している保険の控除にまつわる書類であることを覚えておきましょう。生命保険料控除や地震保険料控除の記入欄は、保険会社が送付する保険料控除証明書を参考にしながら書くとわかりやすいため、従業員自身が証明書を保管しておくと安心です。
配偶者控除に必要な書類
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は「配偶者控除等申告書」に、必要事項を記入して提出します。企業で働く給与所得者本人の所得金額と、パートナーの所得金額によって、控除の適用が決まるため、所得の内訳情報を記入する書類です。
パートナー側の所得金額が給与のみで構成されているかどうかで、適用される金額も変わるため、収入源をチェックしましょう。配当所得や事業所得、家賃収入などの所得を計算する必要があるため、早めに準備しておくことがポイントです。
パートナーがパートの掛け持ちなど複数の勤務先で働いている場合も、全ての給与を計算した金額を書かなければいけません。事前に収入を得ている状況を整理し、書類作成のタイミングで焦らないようにしましょう。
所得金額調整控除申告書の欄については、要件の内容によって記入しなければいけない情報が変わります。所得金額調整控除の金額は、給与を支払っている企業が計算するため、数字の間違いには特に気を付けましょう。
まとめ
この記事では年末調整に必要な書類や書き方を紹介しました。保険料の控除や配偶者控除の申告には、詳細な情報が欠かせません。保険会社から送られてくる証明書や配偶者の源泉徴収票などといった書類を、事前に従業員が用意しておけるように説明しておくと、スムーズな手続きの手助けになります。申告に必要な書類や記入方法などは、従業員一人ひとりの状況により異なるため、給与を支払う事業者側は詳しく対応できるように準備をしておくことが大切です。
-
 引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/
引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/